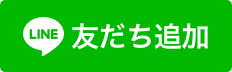プロフィール
心と体と学習の悩みを
トータルサポートするカウンセラー
たかさきひろこ です。
我が子が発達障がい・成績不振・不登校になりかけた経験から、
同じように悩んでいるお母さんたちのサポーターになりたいと
カウンセラーになることを決意。
お母さんたちを笑顔にするカウンセリングを実施中!

さみしかった幼少時代

【生まれて初めての手術】
生まれつきの目の異常があり、入院して、手術を受けた。両親は飲食業を営んでおり、忙しくしていた。
入院時は両親に代わり、父方の祖母が付き添いをしてくれた。祖母はやさしかったけれど、やっぱり母につきそってもらいたかった。
【両親ともっと一緒に過ごしたい】
幼稚園でのお遊戯会は、女子は赤か黄色の帽子を選ぶことが通例になっていたのだが、自分は「緑がいい!」と言い張った。
その主張が通り、緑の帽子をかぶっておどることになった。
とてもはりきって練習をし、両親にも観てもらいたかったが、やはり観に来てくれたのは祖母だった。
祖母のことは好きだったが、両親と一緒に出掛けたり、公園であそんでもらったり、母親に絵本を読んでもらった記憶がない。両親にかまってもらえないさみしさがあった。
不自由でコンプレックスの塊だった学生時代

【目立たない子どもだった】
とにかく、大人しくて目立たない子だった。
学歴コンプレックスがあった。当時は今と違い、成績は相対評価で、少しくらい頑張ってもなかなか結果に表れず、自分の立ち位置はこんなものと諦めの境地だった。
今の子ども達は絶対評価なので、はっきりとがんばりが結果に反映されるので、うらやましい。
【父親から否定され続ける】
父親から否定される毎日だった。
社交的、積極的で明るいことがいいこという価値観で固まっていたので、真反対だった自分は、いつも罵倒されていた。勇気を出して自分の意見を言っても、父の考えと違うと否定された。
一人っ子だったこともあり、逃げ場がなかった。母は、とにかく大人しくて父に逆らうことはできなかった。
大学時代の春休みに、1カ月の間、祖父の入院の付き添いで母と一日交替で病院に寝泊まりしていた。
友人たちは遊びに行ったりして楽しんでいるということを聞くと、ちょっとうらやましかった。
普段から、両親の営んでいる飲食店の手伝いをするために友人の誘いをことわることもあり、なんで自分だけこんなに自由でないのかともんもんとしていた。
子育て奮闘時代 発達障がいかも…

【待望の子どもが誕生、発達障がいの診断が下りた】
30歳までには結婚したいなと言う思いがあり、20代ぎりぎりで入籍。仕事はハードワークで両立ができるとは到底思えなかったので、退職。
自分が一人っ子で寂しかった思いをしたので、子どもは二人は欲しいなと思った。そんな中、待望の子どもの誕生。
初めての子育てに右も左もわからず悪戦苦闘!
母はすでに他界していて、応援も頼めない。
長男は、夜なかなか寝てくれないことがよくあり、寝不足気味だった。
自分がずっと抱っこをしていて、ベッドにおろすとギャーと泣き出す。
へとへとだった。
保健師さんに相談すると、「よくあることですよ、もっと大変な人がたくさんいますよ。」と軽くかわされて、よけいに落ち込む。
長男の誕生から一年半後に長女が誕生。
長女は長男と違って夜すぐに寝付いてくれるので、とっても助かる。
長男は言葉が遅い。指差ししない。
一歳半健診での指摘があり、療育を受けることを決意。
発達障がいの診断が下るまでの間、もんもんとした日々を過ごしていた。
診断が下りたら、すぐに受容ができたかというとそんなことはなかった。
一年くらいは、暗いトンネルの中。
保護者仲間と出会ったことが転機になった。
保護者仲間から、カウンセラーの先生を紹介してもらった。
この先生に出会ったおかげで、トンネルを抜けられたと思う。
つぎつぎと災難に見舞われる40代

【友人の自殺】
小中高と一緒だった友人の自殺を止められなかった。
自分自身、三人目が生まれて、日々の子育てでいっぱいいっぱいで、人のことを考える余裕が本当になかった。
もっと電話で話をきいてあげればよかった。
彼女のことをよく知る共通の友人で集まって、彼女のことについて話しあった。
どうすれば、とめれたのか?
正解ははない。
話しあいのあと、彼女の親族と連絡を取って、お墓参りをしようということになったが、引っ越しをされていて、連絡がとれず実現できていない。
【子育て真っ盛りの中の父の入院】
友人の自殺は父が最初の入院をした時期ともも重なる。
手術のあと、入退院を何度も繰り返す。
大きい病院に転院した時は、大変だった。一番下の子が歩きまわれるようになったので、とにかく目が離せない。
一緒につれていくと、お医者さんと話をするどころではなかった。
とにかく、家に帰るとぐったりしてしまった。
お医者さんの話はきちんと聞きたい。
子どもも歩き回るのはダメ、じっとしていてと言われるのもいやだだろうなあと思った。
そこで、次回からは病院に行くときは、預かってもらえる保育サービスを利用した。
時間単位で預かってもらえるのはありがたい。
人に頼れることは頼る。子育てで受けられるサービスは利用しようと思った。
【夫がうつになった…自殺するかもしれない】
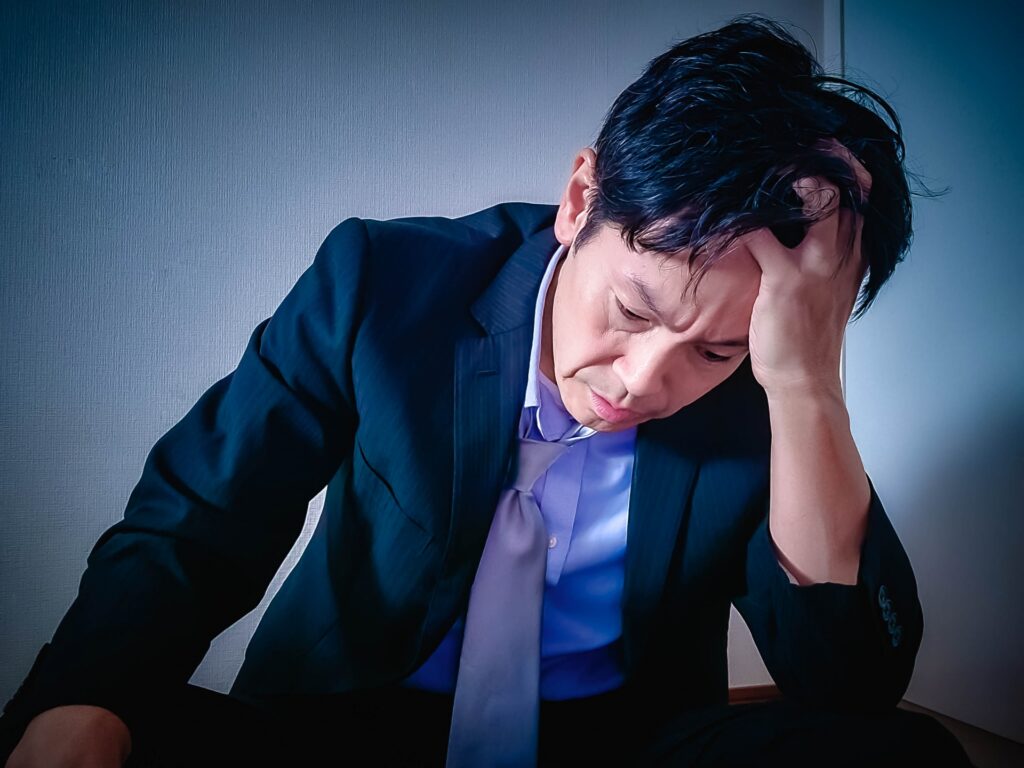
三番目の子が小学校にはいる前くらいに、夫が会社に行けなくなった。
上司が変わったことで、彼の苦手なところばかり指摘されるようになる。
何回報告書を提出してもOKにならない。現場の仕事の腕はピカイチだが、報告などの書類を書くことはもともと苦手だった。
最初は、朝起きて吐き気が止まらない様子だった。これはやはりストレスから来ているにちがいないと確信した。
このまま放っておくと、自殺してしまうかもしれないという予感がした。
ずぐに病院の受診をしないといけないと思った。
長男の発達障がいが縁で知り合った、病院情報に詳しい友人にそのことを相談した。
病院をいくつかピックアップしてくれ、その中ですぐに診察してくれる病院を予約。
受診するとうつの診断。休職することになる。
嘔吐などの症状が収まり、少し前向きになる。
受診した病院のディケアに通わないかとのお誘いがあった。本人も行ってみたいということで、通い始める。
運動したり、おでかけがあったりと楽しいようだ。
大人の放課後ディサービスのような感じだ。
とにかくほっとした。順調に回復している。
精神的に落ち着いてきたので、職場復帰を考えられるようになった。
復職に向けてのプログラムが病院では提供されていない。
長男のことでお世話になっていた相談員さんに相談した。
障がい者職業センターを紹介された。そこで、復職に向けたグループワークや職場への面談の付き添いなどをしていただいた。
日ごろの人脈づくり、ネットワークづくりが大切だと再確認。
相談して行動につないでくれるのはありがたい。
夫も前向きになってくれて、うれしい。
【自転車で転倒、入院生活】

足首をけがして、手術。松葉づえを経験
約一カ月の入院生活だった。
足首をけがして、手術。松葉づえを経験
約一カ月の入院生活だった。
相部屋だったおかげで、知り合いが増えた。
整形外科の病棟で六人部屋だった。
高齢者の入院患者の方がいた。認知面で問題を抱えている方だった。
その方の家族が洗濯ものを持ってきたりして、お世話をしていた。
とても疲れている様子で、仕事場から帰って、すぐに自宅から病院にかけつけている様子だった。
その家族の方が高齢者のプライドを傷つけるような言葉を発していた。
手伝ってくれる人がいないもどかしさ、つらさ・不安・睡眠不足からくるイライラがあるのだなと思った。
そんな人たちの役に立てることができないかと思った。
子どもの成績不振、不登校になるかも… 思春期

【学習障がい・不器用な子達がたくさんいる】
子育てが落ち着き、学習塾でアシスタントを始める。
個別の塾だったので、集団塾でなじめずに変わってくる生徒も多い。
コンパスを上手く使えない、ものさしを使って線を上手く引けないなど不器用な子どもがいることに気付く。
LD(学習障がい)かもしれないと思われるお子さんもいた。
わからないと、プリントをくしゃくしゃにしたり、鉛筆を投げたりするお子さんもいた。
間違っていると指摘すると怒り出す子がいる。
間違っていると言わず、本人が間違っていることに気付くようにヒントを出す。
逆に、間違っていると言わず、本人が気づくようにヒントを出していると、まどろっこしいのか、間違っているならそう言ってという子もいる。
その子その子の性格や特徴を考えて、対応することはむつかしい。
担当の先生がお休みで、代わりにサポートで入るクラスの場合は特に注意が必要だ。
初めての子の場合は、「どんな子なのかな?」とさぐりながら対応する。
【学校へ行きたくない】

次女が小学校に入学。
繊細さを抱えながらも、友達ができて、順調にいっているようにみえた。
そんな二年生になってから。
学校に行きたくないと言ってきた。
給食が辛くてたまらない。
むりやり牛乳で流しこんでいる。
減らしてが言えない。
まさかと思った。幼児期は多弁な方だったので、言えないとは思っていなかった。
盲点だった。
その日はお休みすることにした。
放課後、すぐに先生に電話をして、面談の約束を取り付けた。
先生から「減らす?」と声掛けをしてもらうことにした。
また、残食をなるべく出さないために全体の声掛けをしている。
そのことも気になっているようなので、次女に説明をしておいた。
自分の気持ちを一番大切にして、「食べたくないなら残していいよ」と伝えた。
給食の件が落ち着いて、やれやれと思っていたところ、朝ぐずぐず言うことか何日か続く。
とりあえず、学校には行ったけれど…。
夜にゆっくりと話しだした。
整列して、教室移動するときに靴を踏んだり、押されたりすることがあったらしい。
昨日とかそういうことではなくて、もう一カ月前くらいのことだった。
もっと早く言ってくれていたらなあ…とは思ったけれど、なかなか言い出しにくかったんだよね。
「言ってくれてありがとう。」
先生に相談するか聞いたら、「言わないで」と言われたのでとりあえず見守ることに。
そうこうするうちに、夏休みになった。
二学期になったら、ちょっかいを出されなくなった。
三学期になると、やたらとつかれているのかランドセルを背負ったまま30分くらいそのままの姿勢で転がっている。
色々あるんだろうと思って、何も言わずに見守る。
そのうち、ランドセルをおろして、ゴロゴロし始める。
「疲れた」とよく言う。
「休みたい」と言った日は 「休んでいいよ」と言っている。
その日の時間割をみて、「ああ図工があるからやっぱり行く」
「ああ理科があるからやっぱり行く」と言って行くことも。
好きな科目の授業は楽しみなんだなあ。
あるいは給食のメニューをみて、「○○食べたいからやっぱり行く」とか。
娘は食べることは大好き。
行きたい動機がない時は、「お休みします」の時もある。
その時は休む理由を親子で考える。「今日はどうする?」 「お腹いたいことにする?」
小学校はゆったりと構えていていい。
勉強は家でもできるから。
高学年になって、周りの子ども達も落ち着いたのか、本人も安定しているようだ。
好きな絵を描くことで、心地よい時間を過ごしている。
学校では、絵のリクエストをもらっているようだ。
リクエストをもらうと、パソコンで調べてから、描いている。
好きなことで、認められることで自信がついてきたようだ。
【長女の受験、長男の成績不振 学習スタイル診断との出会い】

子ども達それぞれに効果的な勉強方法がわかる便利なツールはないのか?
それを模索している時に、学習スタイル診断と出会った。
もっと早くこのツールに出会えていれば、長男の受験の時に大変な苦労をしなくてすんだのにと思った。残念…。
しかし、長女の受験には間に合い、活かすことができた。
長女は、情報処理の方法(優位感覚)が全身型、発話型であるという結果だった。
英単語などを覚えるのは、唱えながら書くのが一番記憶に定着する方法だった。
部屋の中を歩き回りながら、ぶつぶつ唱えるのも有効だった。(体全体を使う)
才能のセクションでは、対人的・自己理解・言語理論的なところの数値が高かった。
娘自分では認識できていなかった自分の可能性が可視化された。
自己アピール書を作成するために、学習スタイル診断で自分自身のことを知ることができて、とてもヒントになったと思う。
長男は中学時代に成績不振。不得意な科目、興味のない科目は長時間勉強しても結果がでない。
好きな科目は、進んで勉強するので大丈夫だが、とにかく歴史が覚えられない。意味を理解できていないことをまる暗記するのが苦手。
国語の物語文の人の心情が読み取れないなど色々と課題があった。
長男自身もは長時間勉強しても成績が上がらないことで悩んでいた。
自分で考えてポールベーンの色を変えてノートをまとめたり、色々と工夫をしてみたが、テストの点は全然上がらない!
発達相談でお世話になった大学で、K-ABCやDN-CASの検査をしてもらい、アドバイスをもらった。
一度に検査ができないので、何回も通い、解説をもらうまで約4カ月もかかった。親子ともに必死だった。
視覚的なインプットと概要を理解して、それから詳細に結びつける方法が有効だというアセスメント結果をもらった時は、「これでなんとかなる!」とひと安心した。
歴史はまんがで流れを理解し、細かいところの枝葉をつけていく。
マインドマップも活用した。
この学習方法にたどり着くまで、本当に本人も母も苦労をした。
ずっともんもんとした日々を過ごしていた。悩んでいたのは、中学1年からずっとだったので、大学での相談期間を含めての約2年半にわたる。
学習スタイル診断なら、診断は約30分でパソコンやタブレットでできるし、結果が出るまで4カ月もかからないし、交通費も必要ない。
長女が受けた後に、長男も遅ればせながら学習スタイル診断を行った。
受験に間に合わなかったのが、悔しい…。
情報処理の方法(優位感覚)がスケッチ型、感触型、全身型だった。
マインドマップを使う方法が有効なのは、納得の結果だった。
興味関心のセクションでは、得意や好きのところでは電子工学・数学・物理学は納得の結果だったが、意外な発見は芸術の項目があがっていたことだ。
自分が普段認識していないことがわかることはおもしろい。
苦手な分野に関してはやはり歴史があがっていて、「やっぱりね」という感想だった。
その後、次女と母も学習スタイル診断を受けて、その結果をみると本当に家族それぞれ違う結果が出る。
お互いの違いを知るのに、学習スタイル診断はとても有効なツールだと体感した。
100人いれば100通りの学び方がある。
まさにその通りだなと確信した。
体調不良が続く50代

【顔面麻痺の経験】
このまま治らないかもしれないと不安だった。
飲み薬と注射で約1カ月で回復。
家族が無関心だったのがとってもつらかった。精神的に一番つらい時期は40代のころだったので、なぜ今なんだろうと思った。
あらためて健康であることの大切さを考えるきっかけになった顔面麻痺。
【睡眠と栄養の勉強を始める】

末っ子が高校生になるまでは元気でいたい。
子どものサポートをしたい。
そのために健康である必要性を真剣に考えた。
自分の健康と子ども達の健康のために睡眠と栄養の勉強を始めた。
そうすると、身の回りで思春期になり、体の不調を訴える子ども達が多いのに気づいた。
繊細さゆえなのか、特に消化器系の悩みを抱えるお子さんが本当に多い。
心と体の両面からのサポートの必要性を強く感じた。
【カウンセラーになることを決意】

自分自身が救われた経験から、発達障がい、二次障がい、成績不振、不登校で悩んでいるお子さんをお持ちのお母さんの役に立ちたいと思い始める。
長男の発達障がいがわかった時に、支えてくれたのはカウンセラーの先生だった。この先生のおかげで暗いトンネルを抜けることができた。
長女は、中学校では人間関係で上手くいかず、とても悩んでいた。
また、「自分なんてだめだ」とよく言っていて、自己肯定感が低かった。
親子でどんな高校の選択肢があるのかじっくり調べた。
中学の同級生が誰もいない地元から少し離れた高校に行くことで、人間関係をリセットして、自信を取り戻した。
次女は、学校に行きたくないといった時期もあったが、自分の好きな絵を描くと いうことで、友達や先生方から認めてもらう経験から、自信を取り戻した。
心理セラピーを学ぶことで、子ども達との関係がよくなり、会話も増えて、子ども達の夢のサポートができている。
心と体と学習の悩みをトータルサポートするカウンセラーとして活動中
自分自身の経験から発達障がい、二次障がい、成績不振、不登校で悩んでいるお子さんをお持ちのお母さんの役に立ちたいと思い、
心理セラピー・学習アドバイス・メンタルサポートをしてます
お母さんと子どもの関係がよくなるセラピー
ストレス・不安解消セラピー で
お母さんの心の安定を図ります
「栄養睡眠メソッド」 で
体の不調のお悩みに応えます
「強み探しツール」学習スタイル診断の活用 で
成績不振・不登校や進路選択のお悩みに応えます